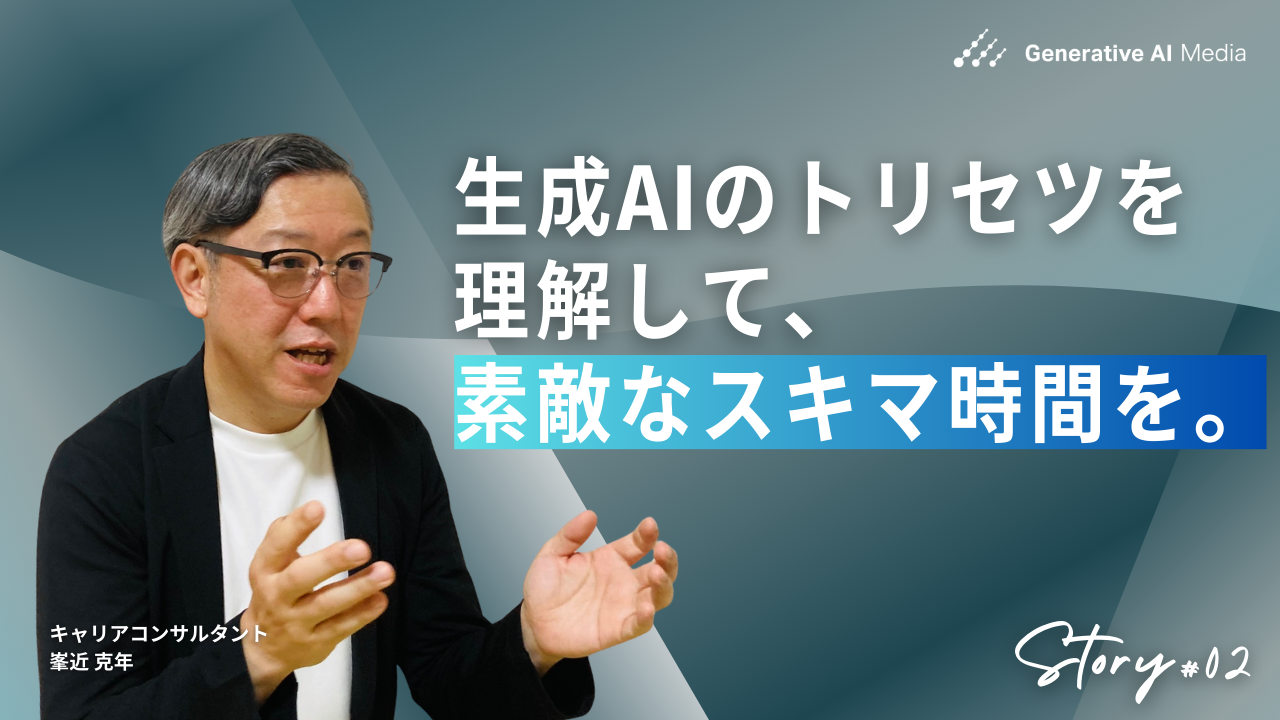転職後のスタートダッシュに成功。生成AIをキャリアの味方につけるコツ【Story #1】

INDEX
企業が生成AIの導入・活用を推進するなか、全てのビジネスパーソンに求められる生成AIリスキリング。実際に生成AIを安全に活用するためのリテラシーやスキルの習得に取り組み、新たなキャリアの形成や市場価値の向上につなげたビジネスパーソンの「ストーリー」に焦点をあてたインタビュー企画をお届けします。
今回は、生成AIリスキリングを通じてCynthialy株式会社への転職を実現した秋元 かおる氏と、採用を担当した同社CEOの國本 知里氏にお話を伺いました。フリーランスや海外生活、育児と仕事の両立など、ユニークなキャリアを持つ秋元さんが感じる生成AIの可能性とは? AI初心者のキャリアに与える影響について深掘りします。
インターネット普及黎明期と同じ雰囲気を感じる生成AI
ー秋元さんの経歴と、現在の職務について教えてください。
秋元:文系の大学を卒業後、中小企業のIT化を支援するベンチャー企業に就職しました。その後、何度か転職し、以前から関心のあった国際協力に携わるためにJICAのボランティアとしてコロンビアへ。コロンビアでは、パソコンの授業を作ったり、生徒を管理するデータベースを改良していました。その後、日本に帰国してからは、JICAの本部でナレッジマネジメントシステムの推進業務を行いました。
出産を機にJICAの仕事を退職後、フリーランスのWebエンジニアとして再出発しました。それからデザイン会社に再就職しましたが、夫の海外駐在によりデザイン会社を退職し、ブラジルに9年間住みました。ブラジル駐在帯同中に日本でDXコンサルティングを行う法人を立ち上げたのですが、帰国後、DXや業務効率化を推進する上で生成AIの知識が不可欠であると感じ、株式会社WarisとCynthialy株式会社(以下、Cynthialy)が共催した生成AIマーケターリスキリングプログラムに参加しました。ここでの出会いをきっかけに、Cynthialyのミッションに深く共感し、入社を決めました。現在は、自分の法人でDX業務を展開する一方、Cynthialyでは企業向けに生成AIに関するコンサルティングや研修を提供する部門で、プロジェクトマネジメント業務を行っています。
ーリスキリングに取り組む前を振り返ると、生成AIに対してどのような印象を持っていましたか?
秋元:JICAの仕事の後、国際協力にIT技術を生かすことを目的としたコミュニティである「ICT4D Lab」に所属しており、そこでAI技術を素晴らしい技術だなと思っていました。もっとも生成AIが登場する前のディープラーニング系の技術が流行していた頃だったので、一部のエンジニアが使う技術と思っていました。その後、ChatGPTがヒットした当時、技術者以外の人がインターネットを使い始めた頃と同じ雰囲気を感じ、これから生成AIは広く使われるようになると確信しました。私の中でのホットテーマになったんです。
私は3人の子どもがいますが、ブラジルに行く前に日本で働いていた頃は通勤や子の体調不良時の対応が大変で、子育てをしながら働く難しさを痛感していました。しかし、生成AIを使えば、家で子育てをしながら生産性を下げずに仕事ができるのではないか、という可能性を強く感じたんです。実際に仕事で活用するようになった今、生成AIはワークライフバランスを実現する手段だ、と実感しています。
ー生成AIは、今まで働きたくても働きづらいと感じていた方にとって強い味方になりそうですね。日々の業務では、どのように生成AIを活用していますか?
秋元:仕事柄、お客さまと会話する際に、技術的なことをわかりやすく伝える必要があります。以前であれば、自分の言葉の引き出しから説明を工夫する必要があったのですが、生成AIを活用すれば想定顧客層を考慮した説明案を出力してくれます。例えば、技術に精通しているお客さまと非IT系のお客さまに対して、同じ説明をするにしてもそれぞれ異なる説明案を出してくれる生成AIは、自分の引き出しを無限に広げられ本当に素晴らしいと感じています。
また、お客さまが作成したプロンプトを改善するためのヒントを、生成AIに教えてもらうこともあります。教えてもらったヒントを参考にして、最後は自分でプロンプトを改善すると、業務効率をさらに改善できる手応えがありますね。

生成AIの基礎知識は、AI初心者のキャリアに選択肢をもたらす
ー秋元さんはリスキリングプログラムを通じて、生成AIパスポートを取得されています。AIリテラシーに関する学習を進めるなかで、印象に残っていることはありますか?
秋元:印象に残っていることが2つあります。まずは生成AIの基礎知識を体系的に学べたことです。Web上で読める生成AIに関する情報は断片的なものが多くなりがちですが、生成AIパスポートの取得に向けた学習では、生成AIの誕生背景から直近の動向までの歴史について順を追ってその成り立ちを理解できました。生成AIパスポートの取得は生成AIを体系的に学ぶ最短ルートだと思います。
もうひとつが、セキュリティなどのリスクに関する内容です。生成AIのリスクについては技術者の方からの観点だけではなく、法律の専門家からの観点も含まれていたのですが、こうした複数の視点が必要だと思いました。
ー秋元さんのようなIT技術に精通されている方からみて、AIリテラシーとデジタルリテラシーの違いをどのように捉えていますか?
秋元:(ルールベースのアルゴリズムのような)従来のITであれば、IF節で分岐した結果として出力される答えは、あらかじめ定められています。対してAIの場合、出力が不確実であり、ブラックボックス化された部分があるので、実在しない答えが出ることがあります。この点がITとAIの大きな違いだと捉えています。
しかし、AIには不確実性があるからこそ、ユーザーが考えもしなかった答えが返ってくるところが面白いとも言えます。思ってもいなかった答えがヒントになって、目から鱗が落ちるような体験ができるのは、生成AIならではと言えるんじゃないでしょうか。だからこそ、デジタルリテラシーに自信がある方にも、AIリテラシーの習得は重要だと感じています。
ー業務を行う中で、生成AIパスポートの取得効果を実感することはありますか?
秋元:私はもともとAIの専門家というわけではなかったので、やはり生成AIパスポート取得によって得られた基礎知識がなければ、お客さまと真摯に向き合うことができなかったと思います。お客さまとのキックオフミーティング後、まずは個別のゴールを設定するのですが、基礎知識がなければゴールまでのアクションを正しく描くことができません。基礎知識があるからこそ応用的な思考がはたらいたり、自分で調べた情報のよしあしを判断できたりするので、お客さまの課題を解決するために新たにインプットするべきことなども把握しやすくなります。
また、自分がもともとはAIの専門家ではなかったことは、お客さまに伴走するうえで大いに役立っていると思っています。多くのビジネスパーソンがAI初心者であるなか、生成AIに関する課題解決では、わからない人・できない人の目線で取り組みを進めることが大切です。私自身がAI初心者からの挑戦を経験しているからこそ、お客さまに寄り添ったご支援ができるのではないかと考えています。そういった意味では、生成AIパスポートの取得はお客さまからの信頼を得る材料となり、AI初心者のキャリアに選択肢を与えてくれるようにも思います。

生成AIパスポート取得で、転職後のスタートダッシュを
ー採用する立場の國本さんからみて、AI初心者であった秋元さんの採用に至った決め手を教えてください。
國本:主な決め手は2つで、ひとつめは問題解決能力や問題発見能力があるところです。生成AIはあくまでツールなので、そのツールを使って問題を発見し解決できる能力が重要だと考えています。
ふたつめは、常に目標を設定して取り組むことができるマインドセットです。秋元さんは自らリスキリングプログラムに応募してAI業界へのキャリアチェンジを目指しましたが、生成AI時代には「どういう自分になりたいか」という思いが大切です。そういうマインドセットがあれば、AI初心者ならではの視点を活かしながら新規サービスも立ち上げてくれるのではないか、という可能性を感じて、一緒に働きたいと思いました。
ー秋元さんが生成AIパスポートの有資格者であることによって、なにかメリットはありましたか?
國本:Cynthialyの場合、創業からまだ3期目なので、タスクが多く、いち早く独り立ちすることを求めています。そうした前提で、生成AIパスポートを取得していることによるメリットとしては、スタートラインに立つまでが早いという印象を持っています。
正直なところ、入社時点では生成AIの知識やスキルはあまり持っている必要はなく、本当に必要なことを入社後に学べばいいという方針です。しかし、やはり生成AIパスポートを持っていることで、入社後の動きが(生成AIパスポートを持っていない人と比べて)違ったように感じています。
ー最後におふたりから、生成AIリスキリングに取り組もうとしている方や、生成AIパスポートの取得を考えている方に対して、応援メッセージをお願いします。
秋元:生成AIは、難しいプログラミングの知識がなくても使えるので、これからさらに普及すると思います。生成AIをなんとなく怖いと思っている方ほど、ぜひ生成AIパスポートを取得して、怖さを払拭してほしいです。取得すれば自信がつき、その後のステップアップが大きく変わると思うので、生成AIを活用してキャリア形成したい人にはぜひおすすめしたいと思います。
私が特に伝えたいのは、男女を問わず育児や介護といった家族の都合が理由で、仕事を離れざるを得ない状況にあった人にこそ、生成AIの活用に挑戦してほしいということです。仕事から離れた期間が長いと、もう自分には何のスキルもない、と自信をなくしている人も少なくないと思います。生成AIが使えるようになると、仕事だけではなくプライベートでも生産的になるので、ぜひ勉強していただきたいです。
國本:生成AIが使えることは、(Microsoft)WordやExcelが使えるのと同じくらい当たり前になってくると思います。「AIに仕事を奪われるのではなくて、AIを使える人に仕事を奪われるのだ」とNVIDIAのジェンスン・フアンCEOが言っていますが、まさにその通りだと思います。こうしたなかで生成AIを学ぶことは、自分の市場価値を高めることになります。
AIを使える人材になるために、生成AIパスポート取得というのは格好の目標になります。本来、学ぶことは手段ではありますが、資格取得というわかりやすいゴールを設定し、あえて目標に掲げることをおすすめしたいですね。そうすれば、その後に見える景色が大きく変わってくると思います。
PROFILE

Cynthialy株式会社 プロジェクトマネジャー
中小企業のIT化支援に従事した後、IT講師兼WEB開発者としてフリーランスで活動。JICAボランティアとしてコロンビアに赴き、現地パートナーと共にIT授業のカリキュラム改訂やデータベースの改良業務に携わる。帰国後はJICAナレッジマネジメントシステム推進業務に従事し、出産を機に退職。フリーランスでWEB開発案件を手がけたのち、デザイン会社に再就職しUI/UX開発やWEB開発などを担当。2015年に夫のブラジル駐在に帯同するため退職し、帯同中にリモートワークを開始。2022年には日本で合同会社コンコルディアを設立し、中小企業経営者の戦略的DXパートナーとしてDX戦略支援や開発業務を展開。2025年からCynthialy株式会社に入社し、生成AIコンサルタント・プロジェクトマネジャーとして複数社の生成AI活用支援を推進している。コロンビア・ブラジルを含む南米に10年居住し、現在は3児の母として仕事と子育てを両立中。