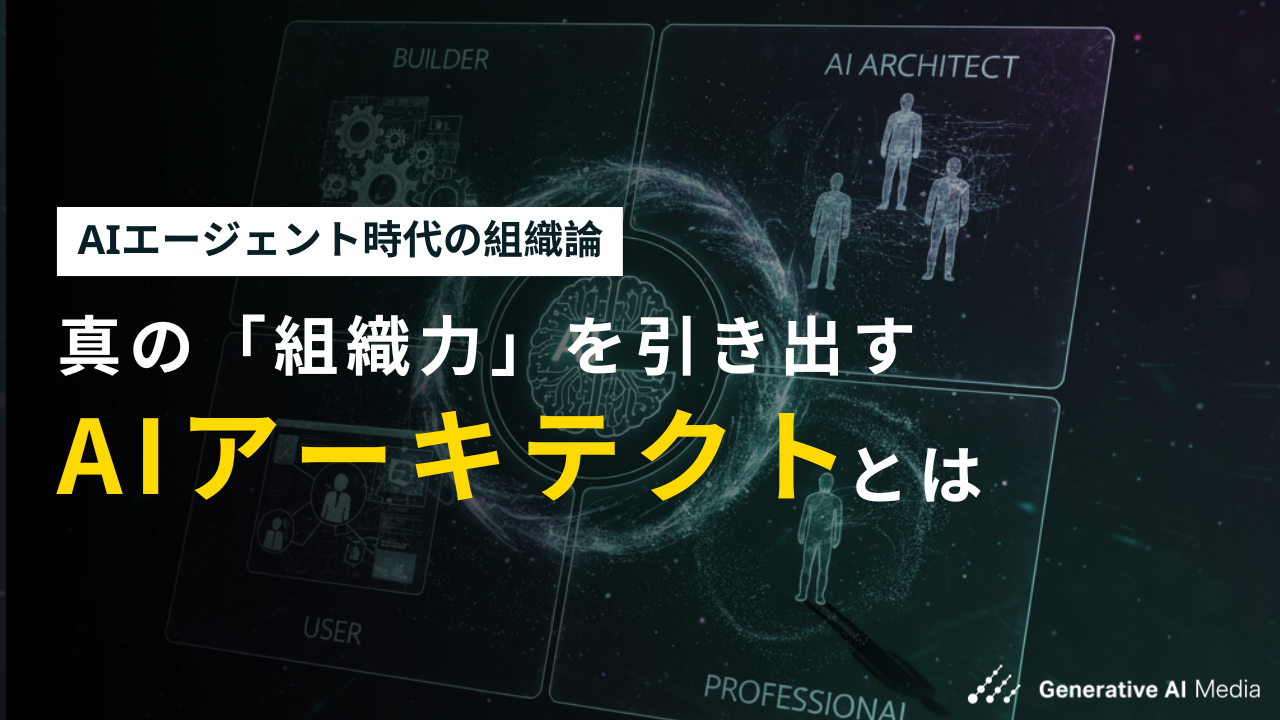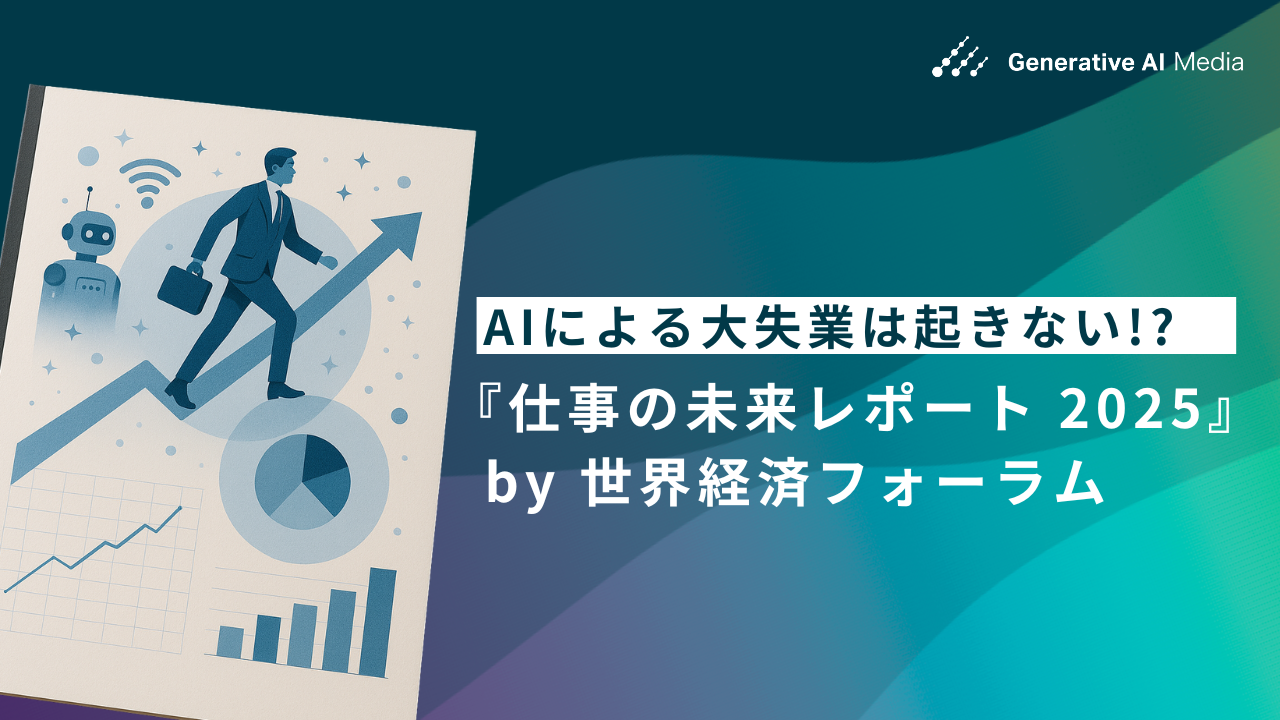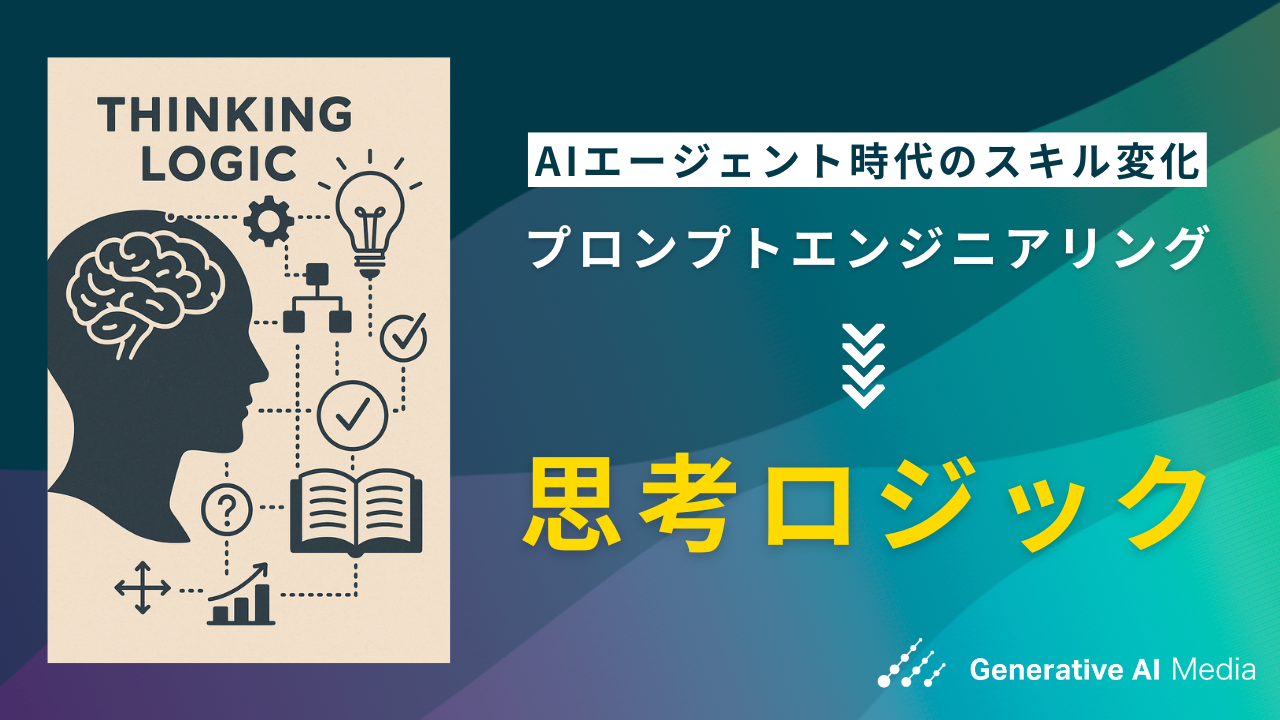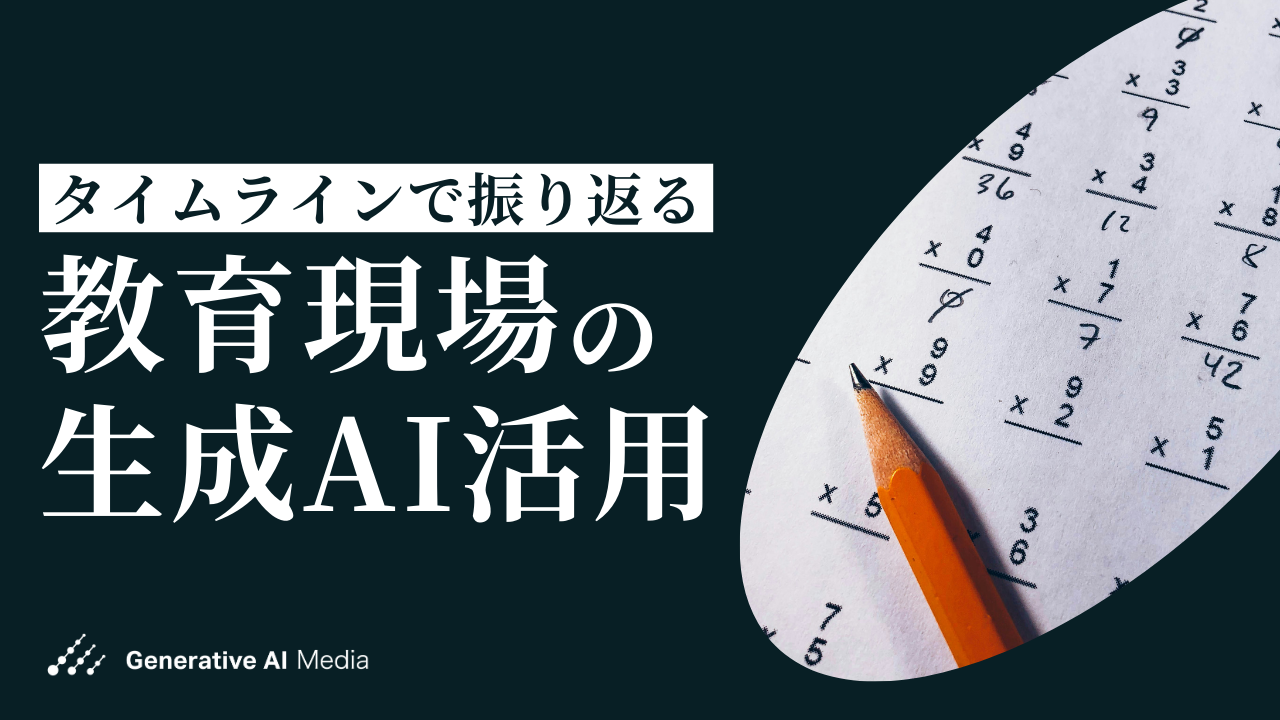【AIトレンド予測2025】3大対話型生成AIメーカーの2024動向総括とAIエージェント時代の展望

INDEX
2024年は、さまざまな生成AIのモデルが公開され進化を遂げたまさに”生成AI飛躍の年”であった。そこで本稿は、同年の生成AI普及度といった統計情報を確認し、また知名度の高い対話型生成AIメーカーであるOpenAI、Google、Microsoftの動向を振り返って、同年を総括したい。
2024年の総括に加えて、2025年における生成AIの重要トレンドとなると予想されるAIエージェントの現状を確かめたうえで、このトレンドの展望も明らかにする。
日本の生成AI普及率はほぼ倍増。ChatGPTが対話型生成AIの首位に
博報堂DYホールディングスのHuman-Centered AI Instituteは2024年11月25日、日本における生成AI普及度などをまとめた『AIと暮らす未来の生活調査』の結果を発表した。発表によると、生成AIの認知と利用について調査したところ、「生成AIを知っているが使ったことがない」層、「生成AIを使ったことがある層」、「生成AIを月1回以上使っている」層の合計が55.7%となり、2023年の28.7%から大幅に増えたことがわかった。
アメリカについては、セントルイス連邦準備銀行、バンダービルト大学、ハーバード・ケネディスクールの共同研究チームが2024年9月、同国の生成AI普及度を調査した『生成AIの急速な普及』を発表した。発表によれば、2024年における生成AIの普及度は40%であった。生成AIの普及開始年をChatGPTが公開された2022年とした場合、2年で40%という普及速度は、コンピュータとインターネットのそれにくらべて非常に速い。インターネットは20%の普及度に達するのに2年を要した。
各種生成AIについては、調査会社アウンコンサルティング株式会社が2024年12月12日、18ヵ国を対象として主要生成AIの検索ボリュームに関する調査結果を発表した。日本やアメリカ、さらにはインドなどを含む18ヵ国のうち、17ヵ国でもっとも検索されたのがChatGPTであった。次いで検索されたのが、Gemini(旧名称のBardも含む)であった。そのほかには、Microsoft Copilot、検索特化型AIのPerplexityが多かった。
アメリカについては、コンサルティング会社First Page Sageが2024年12月3日、同月における同国の対話型生成AIのシェアを発表した。発表によると、ChatGPTがもっとも大きいシェアで59.2%、次いでMicrosoft Copliotの14.4%、そしてGoogle Geminiの13.5%となった。
以上の調査結果を総合すると、2024年では世界的に生成AIの普及が進み、ChatGPT、Gemini、そしてMicrosoft Copilotが知名度が高く、言わば「3大対話型生成AI」として活用されていることがわかる。
2024年における3大対話型生成AIメーカーの動向総括
以下では、2024年における3大対話型生成AIメーカーの主要な動向を年表にまとめる。
OpenAI(ChatGPT)
OpenAIは2024年、ChatGPTに用いるLLMとしてGPT-4oおよび4o-mini、OpenAI o1およびo1-mini、o3およびo3-miniを発表した。GPT-4からGPT-4oまで約13ヵ月、GPT-4oからo1まで約4ヵ月、o1からo3まで約3ヵ月を要しているので、OpenAI製LLMの進化速度は加速していると言えるかもしれない。
| 1/10 | GPT Storeを公開 |
| 2/15 | 動画生成AI「Sora」を発表。発表当初は、一部のテストユーザーのみ利用可能であった。 |
| 4/14 | OpenAI日本法人が設立される。 |
| 5/13 | GPT-4oを発表。 |
| 6/10 | Appleが独自開発した生成AI「Apple Intelligence」を発表。合わせてApple製プラットフォームとChatGPTが連携することも発表。 |
| 7/18 | 費用効率の高い「GPT-4o mini」を発表。 |
| 9/12 | OpenAI o1-previewとその軽量版OpenAI o1-miniを発表。 |
| 10/31 | ChatGPT searchを発表。発表当初はChatGPT PlusおよびTeamのユーザーのみ利用可能であった。 |
| 12/5 | OpenAI o1および月額200USドルの利用プランChatGPT Proを発表。 |
| 12/9 | SoraがChatGPT PlusおよびProユーザー向けに利用開始。 |
| 12/13 | 「Apple Intelligence」からChatGPTへのアクセス提供開始の発表。 |
| 12/19 | ChatGPT searchが無料ユーザーも利用可能となる。 |
| 12/21 | OpenAI o3およびo3-miniを発表。 |
Google(Gemini)
Googleは、2023年12月に発表したGeminiを約1年かけて2.0にバージョンアップした。動画生成AI「Veo」を約7ヵ月かけて2.0にアップデートして、Soraに対抗した。
| 2/1 | 画像生成AI「Imagen 2」を発表。 |
| 2/8 | Gemini Ultra 1.0を発表。 |
| 2/15 | Gemini 1.5を発表。 |
| 2/23 | Imagen 2が不適切な画像を生成することを認め、同AIの利用を停止。 |
| 5/14 | Google I/O 2024にてGemini 1.5 Flashを発表。AIアシスタント「Project Astra」、動画生成AI「Veo」なども発表。 |
| 8/28 | Geminiから利用できる画像生成AI「Imagen 3」を発表。 |
| 9/18 | VeoがYouTube動画制作支援ツール「Dream Screen」から活用可能となることを発表。 |
| 10/3 | 音声アシスタント「Gemini Live」が日本語を含む40ヵ国語で利用可能となる。 |
| 12/11 | Gemini 2.0を発表。AIエージェント・プロジェクト「Project Astra」「Project Mariner」「Jules」も発表。 |
| 12/16 | Soraを凌駕するとされる動画生成モデル「Veo 2」を発表。 |
| 12/20 | 推論能力を強化した「Gemini 2.0 Flash Thinking」を発表。 |
Microsoft(Microsoft Copilot)
MIcrosoftは、Copilotを既存製品に拡張する戦略をとっている。そうした戦略のなかでもCopilot + PCで使えるTeamsやMicrosoft Copilot Studioからは、同社のAIエージェントに注力する姿勢がうかがえる。
| 1/15 | 個人ユーザー向けのCopilot Proの提供と企業向けのCopilot for Microsoft 365のアップデートを発表。 |
| 2/29 | 財務業務向けに機能拡張したMicrosoft Copilot for Financeのパブリックプレビュー版を発表。 |
| 5/20 | 新PCカテゴリー「Copilot+ PC」を発表。 |
| 5/22 | 開発者向けカンファレンスMicrosoft Build 2024において、ミーティング支援AI「Team Copilot」(後に「Teams」に改称)、AIエージェント開発ツール「Microsoft Copilot Studio」を発表。 |
| 6/4 | Copilotを活用したカスタマーサービス向けソリューション「Microsoft Dynamics 365 Contact Center」を発表。 |
| 9/16 | Copilot発表イベント「Microsoft 365 Copilot Wave 2」にてCopilot新機能「Copilot Pages」と「Microsoft 365 Copilot」を発表。 |
| 11/19 | Microsoft Ignite 2024においてTeamsや、アプリケーションを横断してCopiolotの機能を使える「Click to Do」などを紹介。 |
AIエージェント時代の幕開け。ソフトウェア開発業界が先行
2025年における生成AIの動向を展望する際に重要となる概念は、AIエージェントである。AIエージェントとは、テキストや画像といった何らかの情報を出力するのではなく、何らかのタスクを遂行するAIを意味する。この概念を理解するには、Anthropicが2024年10月23日に発表した「computer use」の動作を見るとよい。この機能を解説したYouTube動画では、Claude 3.5 SonnetがCRMから会社情報を探して、リクエストフォームを記入する様子が確認できる。
対話型生成AIをAIエージェントに進化させる動向は、前述の年表からわかるように、GoogleとMicrosoftに顕著に見られる。OpenAIの動向については、ブルームバーグが2024年7月12日に報じている。報道によると、OpenAIはAI開発における以下のような5つのレベルを全社的に共有した。
- レベル1:チャットボット、会話言語を持つAI。
- レベル2:推論者、人間レベルの問題解決力を有するAI。
- レベル3:エージェント、行動を起こすことができるシステム。
- レベル4:イノベーター、発明を支援できるAI。
- レベル5:組織者、組織の仕事ができるAI。
以上のレベル分けに基づけば、OpenAI o1やo3はレベル2に属する現在最高レベルのAIであり、レベル3のエージェントの展開は2025年に本格化するだろう。実際、同年1月15日には、将来のある時点で何かを実行するようにChatGPTに依頼する新機能「Tasks」のベータ版が有料ユーザー向けに公開された。
Tasksは、将来のある時点においてあらかじめ設定したプロンプトを実行するものであり、出力はテキスト等に限定されている。しかしながら、この新機能はOpenAI版AIエージェントの片鱗を垣間見せるものである。
さらに同年1月23日、専用ブラウザにおいてユーザーの指示にしたがってウェブ上のタスクを実行するリサーチプレビュー版Operatorが発表された。この機能を解説したYouTubeのOpenAI公式チャンネルで公開された動画を視聴すると、同機能が食料品配達サービスinstacartで食材を購入する様子が確認できる。
Operatorは、最初はアメリカ在住のChatGPT Proユーザーに提供され、ChatGPT Plus、Team、Enterpriseのユーザーに順次提供し、安全性と使いやすさに確信が持てた時点でChatGPTにも実装する予定だ。
実のところ、AIエージェントはソフトウェア開発業界においてすでに普及が進んでいる。この動向については、LLMアプリ開発フレームワークを提供するLangChainが2024年11月15日に発表した、1,300人以上のエンジニアやプロダクトマネージャーを対象として実施したAIエージェントに関するアンケートが参考になる。なお、同アンケートにおけるAIエージェントの定義は「アプリケーションの制御フローを決定するためにLLMを使用するシステム」とされ、ソフトウェア開発およびコード生成のコンテキストに限定されたものとなっている。
「現在、あなたの会社は稼働中のエージェントを持っているか」という質問に対して、「はい」が51.1%と過半数を超えた。また「現在、あなたの会社は本番環境で使う予定のエージェントを開発しているか」という質問に対しては、「はい」が78.1%であった。
アンケートでは注目しているAIエージェントとして、コード生成AIのCursorやReplitの名前があがった。また、検索特化型AIのPerplexityへの注目度も高かった。
まとめ|2025年は、AIエージェントへの対応が急務となる
本稿が以上で紹介してきたさまざまな動向を総合すると、2025年にはソフトウェア開発業界で起こっているAIエージェントの普及がほかの業界でも起こると予想される。実際にAIエージェントの普及が進んだ場合、起こり得る影響を列挙すると以下のようになるだろう。
- 業務効率化によるコストダウン
- AIエージェントが人手で実行していた既存業務の一部を自動化することで、業務効率化を実現できるだろう。その結果、コストダウンが見込まれる。
- “AIエージェントとの協働”による働き方の変化
- AIエージェントによる既存業務の自動化は、労働時間の短縮をはじめとした働き方の変化をもたらす。こうした変化は、「業務データをAIエージェントと常時連携する」といった”AIエージェントとの協働”を前提とした新たなルーティンをも生み出すだろう。
- 新規のタスクと事業の創出
- AIエージェントを活用することで、人手では不可能だったタスクが実行可能となる。こうした新規タスクの実現は、新規事業の創出に寄与するだろう。新規タスク考案に際しては、AIエージェントと企業内の既存アプリやデータの連携がカギとなるだろう。
- AIエージェント活用スキルの必要性
- タスクを遂行するAIエージェントを活用するには、テキストや画像の出力を指示する従来のプロンプトエンジニアリングだけでは不十分な可能性がある。それゆえ、AIエージェントに指示するための新たなスキルが必要となり得る。こうした新たなスキルを有する人材の育成が、企業の競争力を左右するだろう。
以上のような影響を予見しながら、各企業のAI活用推進担当者はAIエージェントに関する動向を注視して、自社の業務に活用できそうな場合には早期に試用を検討すべきであろう。
(記事著者:吉本幸記)